高村薫
作家的時評集 2000-2007
ガイド
今でも全く古くない、むしろ読み返すべき
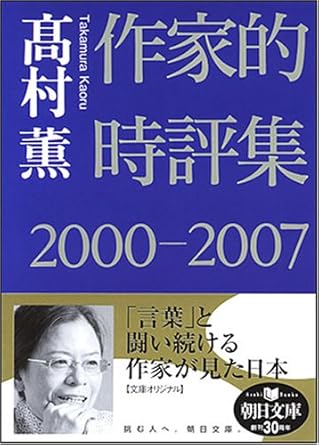
書誌
| author | 高村薫 |
| publisher | 朝日文庫 |
| year | 2007 |
| price | 700+tax |
| isbn | 978-4-02-264414-5 |
履歴
| editor | 唯野 |
| 2025.3.18 | 読了 |
| 2025.3.18 | 公開 |
20年前に書かれた文章で発せられた警鐘が弱まるどころか逆に状況はひどくなり、より強くなって響いてくる辺りに、本当に日本はおかしくなってしまったのだな、という気持ちが先に来た。例えば小泉首相に見る熱狂と言葉の乖離は安倍首相を経てさらに強化され、もはや政治家にビジョンなと求めるのも無理な時代を感じさせる。また、あらゆる場面でのモラルや矜持も下落する一方のため、既に取り返しの付かない状況にある。なぜなら、自浄作用が働かない時点で、先行きは暗いというほかはなく、それが進めばトランプ2.0のような政治家がそのうち日本にも登場するのであろう。
とはいえ全体に通じる部分という視点で見れば、要は「言葉の力の減退に伴う無関心の広がり」ということに集約されるのではないかと思われる。もちろん著者もその点について重ねて述べているが、これは全くその通りだろう。結局のところ、個人が自分のことしか考えられなくなった帰結として、社会全体、もしくは弱者や少数者への思いも馳せられないという悪循環が続くからである。いみじくも著者がp314で語っている通りである。
成熟した文明社会を築くためには、やはり言葉が重要だろうと思います。言葉の機能が失われると、社会的な広がりが実感できない。世界がどんな姿をしているか、自分は何を感じ、何を望むのか。それを捉えるのは言葉だからです。言葉で捉える過程がなければ、人間はただ刺激に反応するだけの動物的存在に成り下がってしまいます。
だからこそ、私たちの世代は言葉を今以上に減らさない努力をしなければならない。たとえば、外交というのは戦略ですが、戦略はまさに言葉です。-/-
文化の面も同様で、今日本から画期的な経済理論や社会学理論が出てこないでしょう。学力の面でも日本は確実に立ち行かなくなっているのですが、これも言葉の文化を維持して育てる土壌が失われたからだろうと思います。そして、言葉の蓄積を守る土壌がないところには新たな蓄積も生まれませんから、知識はさらに失われるほかありません。そうなると当然高等教育のレベルは下がるし、日本は技術立国を目指すと言っていますけれど、技術者を育てる土壌もなくなる。言葉がなくなるということは、日本の根本がなくなることとイコールなのです。
最近は本も高くなってしまい、それがさらにまた読書や活字を遠ざけ、著者の危惧する状況を悪化させるのだろう。
抄録
16
子どものころ、わたくしはこうした日本の新年を、伝統的な美しい形式の一つだと思い、それなりに納得していたものだが、社会人になってから、あるとき考えた。ひょっとしたら日本人の多くは、新年が開けたと同時に旧年は水に流れるものと、ほんとうに思い込んでいるのかもしれない、と。「この国は」とあらためて思いを馳せるどころか、個々の気持ちの持ちようから国の大事まで、日本の新年は旧年をチャラにしてすえべてをリセットするための、便利なスイッチのようだ、と。
18
デモや暴動が起こる代わりに、世相が暗いほど初詣が賑わい、賽銭が増えるというわたくしたちの国民性の穏やかさや善良さは、世界に誇っていいが、そうして半世紀以上にわたって、何があっても静かな新年を迎え続けてきた結果、実は消えることなく積み重なってきた国や経済や社会の制度疲労は、いくら新年モードに切り換えても、ついに目を覆えないところまで来てしまったのだと思う。
21
ここ数年、社会や時代への違和感が年々大きくなり、一つひとつ挙げていくと切りがないほどだが、最近そうしたわたくしの違和感の周りには「嘘」という一語が浮かんでいる。
